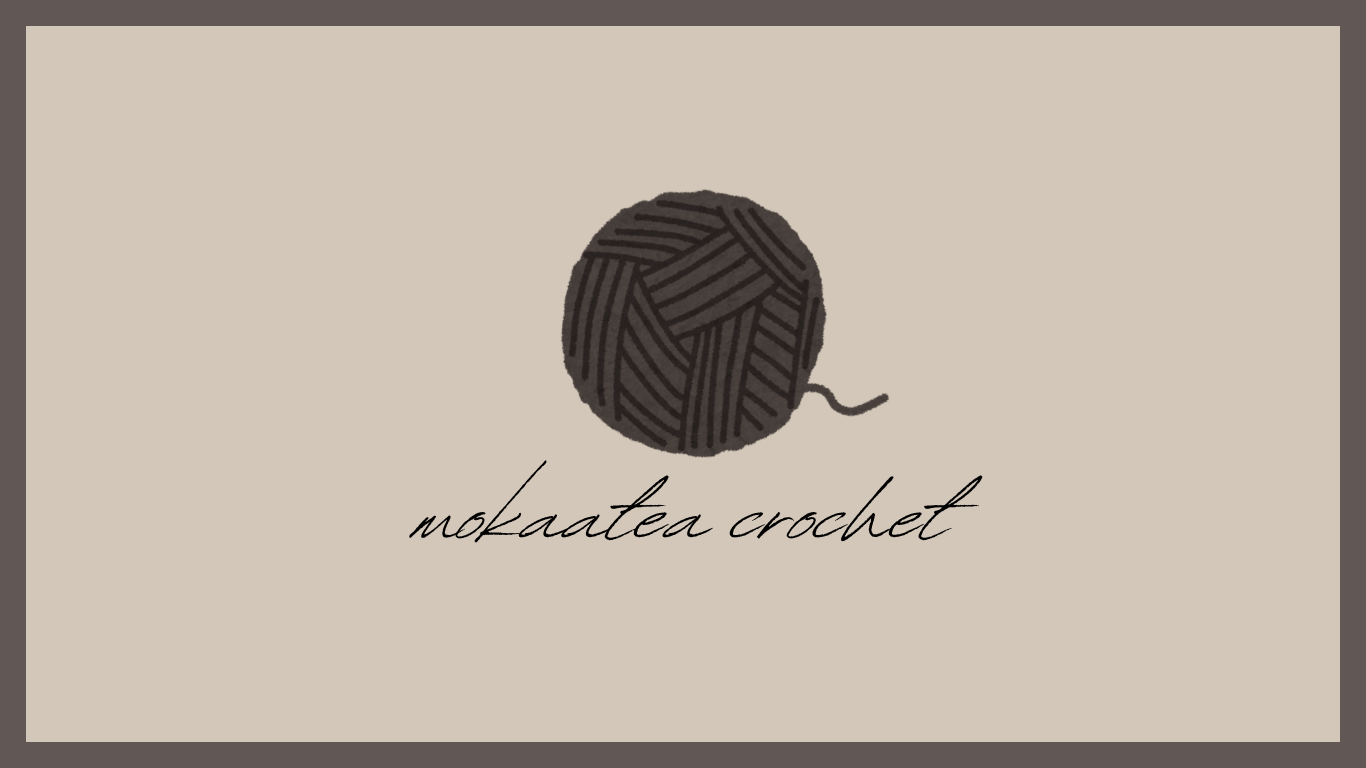かぎ針編みを始めたい、または始めたばかりの方が最初につまずきやすいのが、編み図の解読です。たくさんの種類がある記号の編み方や見方がわからず、途中で挫折してしまった経験はありませんか?この記事では、そんなお悩みを解決するため、基本的な記号の一覧から、複雑な模様編みで使われるものまで、かぎ針編みの記号を網羅的に解説します。簡単な記号はもちろん、増し目を意味するvや減らし目、さらには大手メーカーのハマナカが使用する記号までカバー。便利な、かぎ針編み目記号辞典アプリも紹介し、あなたの作品作りを力強くサポートします。
- かぎ針編みの基本的な記号の見方と意味がわかる
- 記号ごとの正しい編み方をマスターできる
- 増減や模様編みなど応用的な記号が理解できる
- 編み図の読解に役立つ便利なツールを知れる
基本から学ぶかぎ針編み 記号
- 編み図の基本的な見方
- まず覚えたい簡単な編み目記号
- 基本的な編み目記号の種類
- すぐわかる編み目記号一覧
- 記号ごとの基本的な編み方
編み図の基本的な見方

かぎ針編みの編み図は、作品を編むための設計図です。記号の羅列に見えるかもしれませんが、基本的なルールさえ覚えてしまえば、誰でも読み解くことが可能になります。編み図を理解できると、作れる作品の幅が格段に広がります。
まず、かぎ針編みの編み図には、「輪の編み図」と「往復編みの編み図」の2種類があることを理解しましょう。
編み図の種類と見る方向
- 輪の編み図:コースターや帽子のトップなど、円形に編む作品で使われます。中心から外側に向かって、反時計回りに編み図を追いかけます。各段の数字が編む順番を示しています。
- 往復編みの編み図:マフラーやブランケットなど、平面的に四角く編む作品で使われます。下から上に向かって、1段ごとに左右交互に編み進めます。奇数段は右から左へ、偶数段は左から右へと見ます。
編み図は、これらのルールに沿って、編み始める位置から順番に記号を追っていきます。立ち上がりの鎖編みから始まり、どの目にどの編み方を何回行うかが、すべて記号で示されています。最初のうちは難しく感じるかもしれませんが、実際に手を動かしながら編み図を追うと、構造が理解しやすくなりますよ。
まず覚えたい簡単な編み目記号
かぎ針編みには多くの記号がありますが、全ての作品が複雑な記号でできているわけではありません。実は、ごく少数の簡単な基本記号を覚えるだけで、マフラーやコースターといったシンプルな作品は十分に作れます。
初心者がまず最初にマスターすべき、最も基本的で重要な記号は以下の3つです。
最優先で覚えるべき基本の3記号
- 鎖編み(くさりあみ):すべての編み方の基礎となる、編み始めや立ち上がりに使われる記号です。楕円(○)で表されます。
- 細編み(こまあみ):編み地が詰まって丈夫になる、最も基本的な編み方の一つです。記号はバツ(✕)やプラス(+)で示されます。
- 長編み(ながあみ):高さが出るため、速く編み進められるのが特徴の編み方です。T字に斜線が1本入った(〒のような)記号で表されます。
これに「引き抜き編み」を加えた4つを覚えれば、基本的な編み物は形になります。多くの複雑な模様編みも、これらの基本の編み方の組み合わせや応用で成り立っています。まずはこれらの簡単な記号と編み方をしっかりとマスターすることが、上達への一番の近道と言えるでしょう。
最初は難しく考えずに、鎖編みと細編みだけで四角いコースターを編んでみるのがおすすめです。一つの作品を完成させることで、自信がつき、次のステップに進む意欲が湧いてきますよ!
基本的な編み目記号の種類
かぎ針編みの記号には、その編み方の高さや形状によって様々な種類が存在します。ここでは、基本的な編み方の記号を高さの順に紹介します。編み方の高さが変わると、記号の形も変わるというルールを覚えておくと、未知の記号が出てきたときにも推測しやすくなります。
基本となる編み方は、主に以下の通りです。
- 引き抜き編み:高さを出さずに目と目を繋いだり、段の終わりで輪を閉じたりするのに使います。記号は黒い点(●)で表されます。
- 細編み:前述の通り、基本的な編み方です。記号はバツ(✕)です。
- 中長編み:細編みと長編みの中間の高さの編み方です。記号はTの字で表されます。
- 長編み:高さのある基本的な編み方です。記号はT字に斜線1本(〒)です。
- 長々編み:長編みよりもさらに高さのある編み方です。記号はT字に斜線2本です。斜線の数が増えるほど、高さが増していきます。
これらの記号は、作品の土台となる最も基本的な要素です。それぞれの編み方の特徴を理解し、使い分けることで、作品に表情が生まれます。例えば、細編みだけで編むとしっかりした固めの編み地に、長編みだけで編むと柔らかくしなやかな編み地になります。
すぐわかる編み目記号一覧
ここでは、これまで紹介した基本的な編み目記号を一覧表にまとめました。編み図を見ながら「この記号は何だっけ?」となったときに、すぐに確認できるよう、ぜひご活用ください。

記号のバリエーションについて
編み図を公開している書籍や作家さんによって、細編みを「✕」で表記する場合と「+」で表記する場合があるなど、一部の記号にバリエーションが存在します。編み図を見るときは、必ず最初にその編み図で使われている記号の凡例を確認する習慣をつけましょう。
記号ごとの基本的な編み方
記号の意味がわかったら、次はその記号が示す編み方を習得しましょう。ここでは、特に重要な「鎖編み」「細編み」「長編み」の3つの編み方の手順を解説します。
鎖編みの編み方
- 作り目を作り、かぎ針に糸をかけます。
- かけた糸を、かぎ針にかかっているループの中から引き抜きます。
- これで鎖編みが1目完成です。これを繰り返します。
細編みの編み方
- 編み地(または鎖編み)に針を入れ、糸をかけて引き出します。
- かぎ針に2本のループがかかった状態になります。
- もう一度かぎ針に糸をかけ、その2本のループを一度に引き抜きます。
長編みの編み方
- かぎ針に糸を1回かけます。
- 編み地に針を入れ、糸をかけて引き出します。
- かぎ針に3本のループがかかった状態になります。
- かぎ針に糸をかけ、手前の2本のループだけを引き抜きます。(残り2ループ)
- 再度かぎ針に糸をかけ、残りの2本のループを引き抜きます。
これらの編み方を動画サイトなどで検索すると、実際の指の動きや糸の扱い方がよくわかります。最初はゆっくりで構いませんので、一つ一つの動作を丁寧に行うことが、きれいな編み地を作るための鍵となります。
応用までわかるかぎ針編み 記号
- 増し目記号「v」の意味と編み方
- 減らし目の記号とテクニック
- 模様編みで使われる特殊な記号
- ハマナカの編み図に出てくる記号
- 便利な記号辞典アプリの紹介
増し目記号「v」の意味と編み方
作品に丸みを持たせたり、円を大きくしたり、フレアのように広げたりする際に不可欠なのが「増し目」です。編み図では、アルファベットの「v」のような記号で表されることが多く、これは「1つの目に2つの目を編み入れる」ことを意味します。
例えば、細編みの編み地に「v」という記号があれば、「前の段の1つの細編みの目に、細編みを2目編み入れる」という指示になります。同様に、長編みの編み地に「v」の記号があれば、1つの目に長編みを2目編み入れます。
増し目の効果
増し目を規則的に行うことで、編み地を平らな円形に広げることができます。これは、帽子やコースター、あみぐるみの頭部などを編む際の基本的なテクニックです。逆に、増し目を行う間隔を狭めると、編み地にフリルが生まれます。
記号「v」は、厳密には細編み2目一度の増し目を指すことが多いですが、文脈によって中長編みや長編みの増し目を意味することもあります。どの編み方で増し目をするかは、編み図の他の部分や凡例を見て判断しましょう。
減らし目の記号とテクニック
増し目とは逆に、目を減らして編み地をすぼめたり、形を整えたりする際に使うのが「減らし目」です。編み図では、逆V字の「Λ」のような記号で表されることが多く、これは「2つの目を1つにまとめる」ことを意味します。
例えば、細編みの減らし目の場合、以下の手順で行います。
- 1つ目の目に針を入れ、糸をかけて引き出す。(ループ2本)
- そのまま、2つ目の目に針を入れ、糸をかけて引き出す。(ループ3本)
- 最後に、かぎ針に糸をかけ、針にかかっている3本のループを一度に引き抜きます。
この操作により、前の段の2つの目が、新しい段では1つの目にまとまります。この減らし目のテクニックは、あみぐるみの底を閉じるときや、帽子のトップを絞るとき、洋服の袖ぐりや襟ぐりをカーブさせるときなどに使われる非常に重要な技術です。
減らし目をするときは、きつく編みすぎないのがきれいに仕上げるコツです。特に最後の引き抜きの際に、糸を引き締めすぎると編み地が歪んでしまうことがあるので注意しましょう。
模様編みで使われる特殊な記号
基本的な編み方に慣れてきたら、ぜひ模様編みに挑戦してみましょう。模様編みには、玉編みやパプコーン編み、引き上げ編みといった、少し特殊な記号が登場します。これらをマスターすると、作品に立体感や豊かな表情を与えることができます。
代表的な模様編みの記号
- 玉編み:長編みの未完成な形を同じ目に複数回編み入れ、最後に一度に引き抜く編み方。ぷっくりとした丸い形が特徴です。
- パプコーン編み:同じ目に長編みを5本など複数編み入れた後、最初の長編みの頭に針を入れて引き抜き、コーンのような立体的な形を作ります。
- 引き上げ編み:前の段の目の足全体をすくって編む方法。「表引き上げ編み」と「裏引き上げ編み」があり、リブ編みのような凹凸のある編み地が作れます。
- 交差編み:長編みなどを交差させて編むことで、ケーブル模様のような縄状の模様を作ります。
これらの記号は一見すると複雑ですが、実際は基本の編み方の応用です。一つ一つの手順を分解して考えれば、決して難しいものではありません。模様編みが一つできるようになるだけで、作れる作品のデザイン性が飛躍的に向上します。
ハマナカの編み図に出てくる記号
日本国内で手芸用品を展開する大手メーカーハマナカの編み物キットや書籍を利用する方も多いでしょう。ハマナカの編み図で使われる記号は、JIS(日本産業規格)が定める標準的な記号に準拠しているため、非常に信頼性が高く、広く一般的に使われています。
ハマナカの公式サイトでは、基本的な編み目記号とその編み方を動画で丁寧に解説しており、初心者にとって大変参考になります。もしハマナカのキットなどでわからない記号が出てきた場合は、まず公式サイトの情報を確認するのがおすすめです。
ハマナカの編み図の特徴として、記号だけでなく、段数や目数、立ち上がりの位置などが非常に分かりやすく丁寧に記載されている点が挙げられます。これにより、編み進める中で迷子になりにくく、初心者でも安心して作品作りに取り組むことができます。
他の出版社の編み図と記号が若干異なる可能性はゼロではありませんが、ハマナカで使われている記号は日本のデファクトスタンダード(事実上の標準)と言えるため、これを基準に覚えておけば、ほとんどの編み図に対応できるでしょう。
便利な記号辞典アプリの紹介
外出先で編み物をしているときや、手元に教本がないときに「この記号、どう編むんだっけ?」と困った経験はありませんか。そんなときに非常に便利なのが、スマートフォンのかぎ針編み目記号辞典アプリです。
これらのアプリには、数多くの編み目記号が登録されており、記号の形や名称から簡単に検索することができます。多くのアプリでは、記号の意味だけでなく、編み方を解説するイラストや動画へのリンクも用意されているため、その場で疑問を解決することが可能です。
アプリを利用するメリット
- いつでもどこでも、手軽に記号を調べられる。
- 動画で編み方を確認できるため、理解しやすい。
- 基本的な記号から特殊な記号まで、幅広く網羅されていることが多い。
- 無料で利用できるアプリも多数存在する。
App StoreやGoogle Playで「かぎ針編み 記号」などと検索すれば、複数のアプリが見つかります。レビューなどを参考に、自分に合った使いやすいアプリを一つインストールしておくと、編み物ライフがより快適でスムーズになること間違いなしです。
かぎ針編み 記号の総まとめ
- かぎ針編みの編み図には輪編みと往復編みがある
- 初心者は鎖編み・細編み・長編みをまず覚えるのが良い
- 記号は編み方の高さによって形が変わるルールがある
- 編み図の記号は出版社や作家により若干の違いがあるため凡例を確認する
- 増し目は一つの目に複数の目を編み入れることで記号は「v」
- 模様編みを覚えると作品の表現力が格段にアップする
- 玉編みやパプコーン編みは立体的な模様が作れる
- ハマナカの記号は日本の標準的なもので信頼性が高い
- 困ったときはスマホの記号辞典アプリが非常に便利
- アプリは動画解説付きのものも多く理解を助ける
- 基本的な記号は限られているので焦らず少しずつ覚えることが大切
- 記号が読めると作れる作品の幅が大きく広がる
- 実際に手を動かしながら編み図を追うと理解が深まる
- 編み物ライフをより楽しむために記号の習得は不可欠
かぎ針編み作家𝘮𝘰𝘬𝘢𝘢𝘵𝘦𝘢です。
編み図がなくても編める、気軽で自由なかぎ針編みを提案しています。
はじめての方でも、暮らしの中でそっと楽しめるものづくりを目指しています。